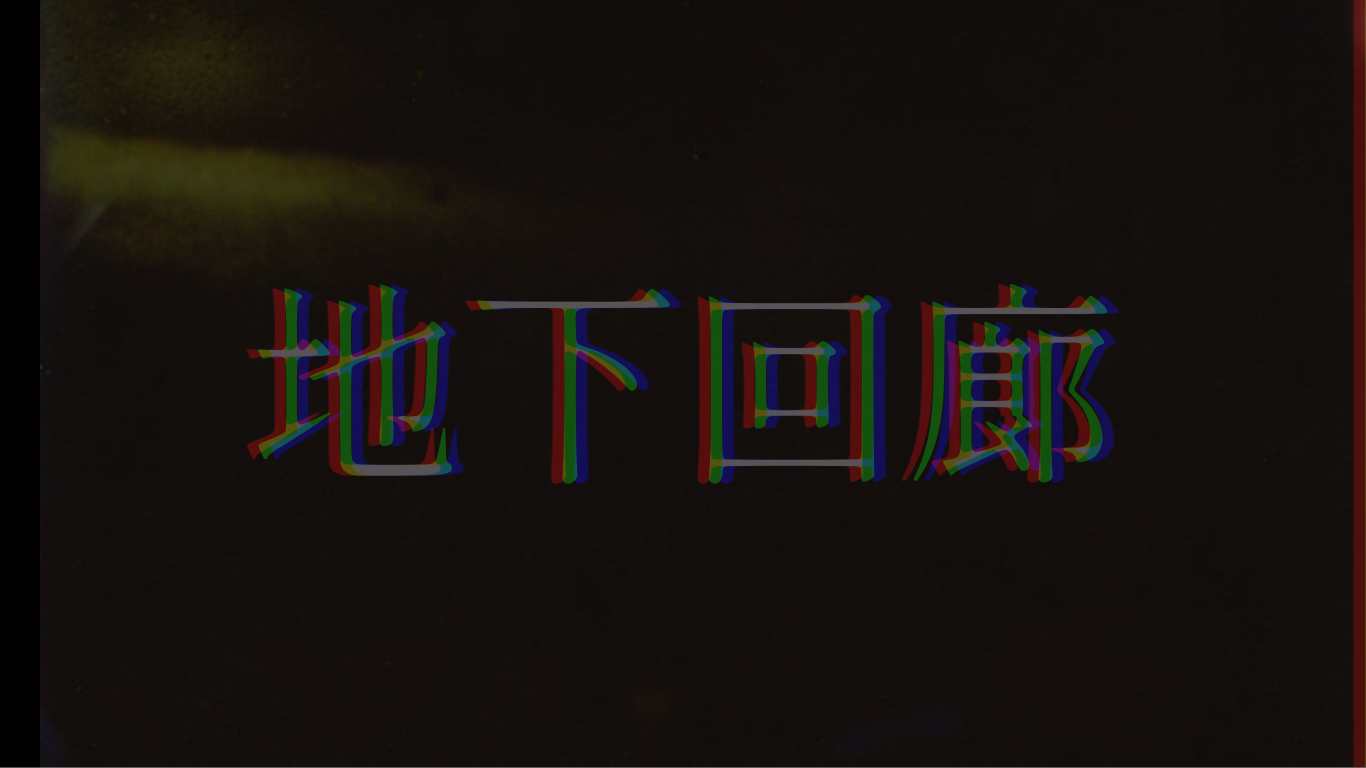エンドロール.クライシス

日の光が浅く、ノウルを焼き殺していくのを見ていた。
陽光が私たちを殺すことは知っていた。でも、ノウルが私のために死ぬなんて、そんな事は知らなかった。
「かえ、す、よ」
ノウルの声は焼けただれていた。長い腕を伸ばして、ノウルは影の中の私にリボンを渡そうとした。
「……こんなの、いらない」
こんなもののために、ノウルが死ぬなんて、知らなかった。このリボンは、ノウルが私の青个歳の誕生日に、くれたものだ。大切なものだった。
「いら、なかっ、た?」
ノウルは灼熱の中で寂しく笑ったように見えた。数秒前、風が吹いた。私の大切なリボンは空中に舞い上がる。ノウルは手を伸ばし、六本目の脚を踏み外す。崖下へ転げ落ちる。陽の光の満ちる、崖の下へ。そしてその時と同じように強風が吹き抜けた。力を失ったノウルの手からリボンが離れて、空に舞い、遠くへ消えた。
「いらないよ」
「そっ、か」
私は、初めてノウルを憎んだ。これから、青が赤へ、白へ巡るくらい長く、私たちには時間があったはずだ。それなのに。
「ノウルのせいだ」
「ウィ、タ……」
「こんなばかなことするから」
「ごめ、ん、ね」
「ぜんぶ台無しだ」
私は睨みつけた。陽がノウルを焼き尽くす。骨が覗く。百五対の肋が見えてくる。その白が輝く。
触れるまでもなく、手を伸ばす。
「ノウルなんてきらいだ」
私は踏み出す。
初めて、暖かさというものを知る。次に熱さを、焼ける痛みを知る。ぐるぐると、目が眩む。
あんなもののために。
「ウィ、……タ」
「ノウルなんて、ノウルなんてきらいだ!」
「泣か、な、いで……」
「きらいだ……」
陽の光の眩しく、巨大な空の下、私は初めて星を見上げる。
「……あんなもの、いらない……ノウルが……」
そこで喉が焼け、私は言葉を永久に失う。涙が消える前に、私はノウルを抱きしめる。骨が崩れ落ち、血がじゅくじゅくと音を立てる。青い血。青から赤へ、白へ巡るまで。
陽の光が焼く。罰に罪を重ねる。融け合い、私たちは輝きに全てを捧げる。そんなことはどうでもよかった。何もいらなかった。赦しも、償いも。
空を舞った青いリボンが、陽光を一瞬過ぎった。それが最後だった。