地下回廊
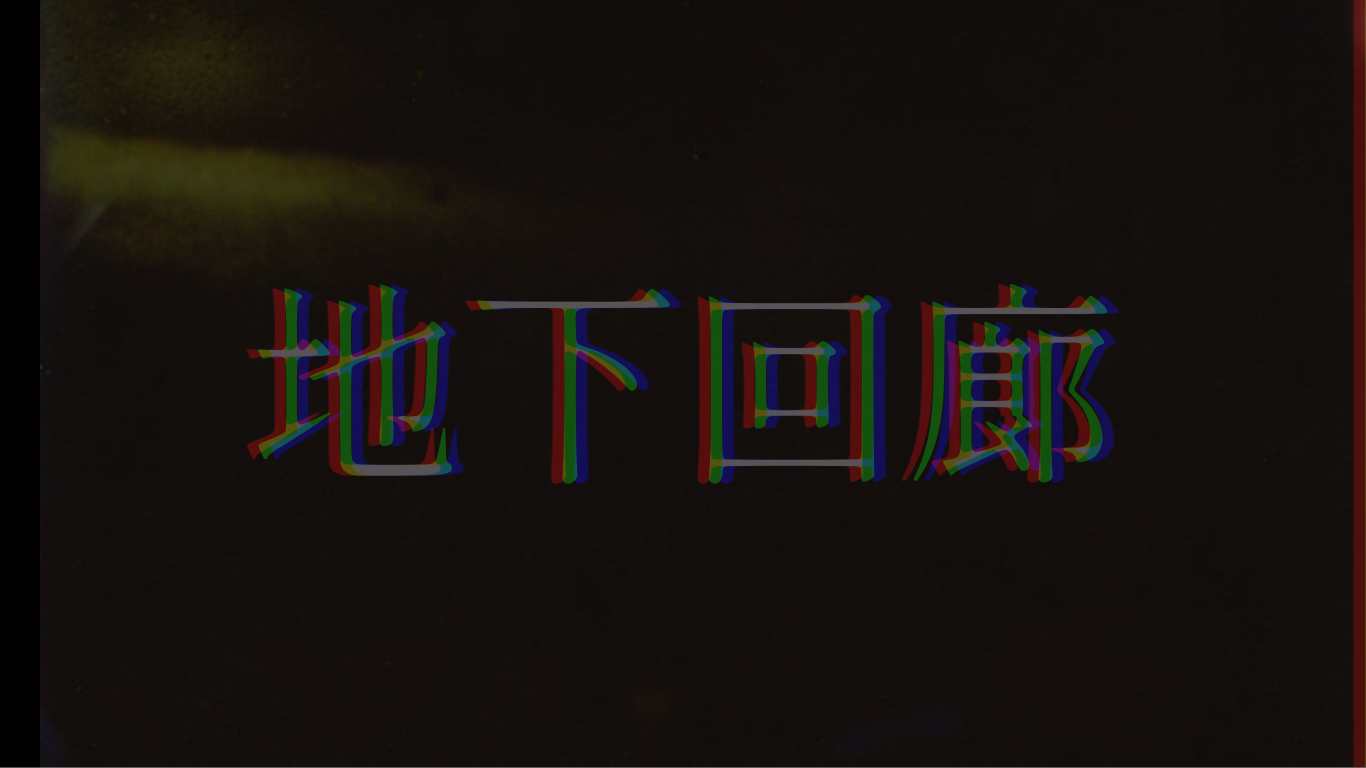
回廊が、長く暗い回廊が続いている。
地下室への道をぼくは歩いていた。かび臭い通路、生き物の這う気配、滴る雨漏れ、外は嵐だ。
蜘蛛を踏みつけた。回廊のどこかで、壁を引っ掻くような音がしていた。
昨日、夢を見た。暗い地の底で、血まみれになった壁、天井、手のひら。不安は、夢になって現れると誰かに聞いたことがある。何度も悪夢に跳ね起きる夜の冷たさ、静けさ、恐ろしさ、そして途方もない長さは、牙も爪もないのにぼくを着実に絞め殺そうとする。夢だったと気づき、ほっとして顔を上げると、天井から吊り下がる何十もの首吊り死体が、窓から吹く夜風に揺れる。吊り縄が首に喰いつく蛇に見える。くるくると滑稽に回って、一斉にこっちを向く。その瞬間、また目が覚める。ぼくを呼ぶ声がする。
ぼくは地下回廊を歩いていた。この回廊は地下室を取り囲んで一周する。その奥に、地下室の入口がある。その中にカガシャが待っている。ぼくは歩いた。二つ目の角、水たまりを踏みつけると、弾けた水しぶきが、靴を濡らした。
見上げてはいけない、振り返ってはいけない。
ぼくはみっつめの角を曲がった。すると奥にろうそくの日が揺れていた。地下室の入口だった。ぼくはそこまで歩いていくと、ランタンを壁にかけた。扉を押し開けた。
ためらってはいけない。これは何度目だろう、とふと思った。
部屋の中は、明るかった。カガシャが待っていた。赤い蛇が、部屋を這いずっていた。
「やあ、ラトス。待ってたよ」
カガシャは椅子から立ち上がった。マグカップの白さが目に眩しい。ぼくは向かい合って置かれた椅子に腰掛けた。
「……頼みがあってきたんだ」
「僕が呼んだから来たんじゃないのかい」
カガシャはぼくを見下ろすと、目を細めて笑った。陶器のような肌が病的に青白い。
「知らないよ。そんなの関係ない」
「まあ、僕はどっちでもいいけどね」
カガシャはポットから、もう一つの空のマグカップに紅茶を注いだ。透き通った赤い液体が、天井の灯りを照り返した。
「最近……悪夢ばかり見るんだ」
ぼくはつぶやいた。カガシャは微かに笑ったようだった。
「どんな悪夢を?」
カガシャがポットを置き、カップを差し出した。ぼくはその水面を見つめた。揺れて、反射する。赤い蛇が映る。
「言葉が出てこないんだ」
カガシャはカップをぼくの前に置いた。
「言葉が、出てこない?」
背もたれに背をゆっくり預けた。頼みごとをする前に、下らないことを話したくなった。
「母さんが、ぼくを呼んでるんだけどね」
ぼくは話し始める。赤い蛇が這う部屋が、引きずられて傾ぐような気がする。灯りが点滅しているのかぼくの目が眩んでいるのか分からなくなる。
「母さんは、昔……首を吊った兄さんを見つけてから、おかしくなった。その時さ、眼が合って、その眼に睨まれたっていうんだ。涙のように血を流した眼に。この人殺しって言われたって言うんだ、その話を、毎日、毎朝、毎晩、聞かされる」
「きみの兄が死んだのは、五年前だったかな?」
「そうさ、それから五年間、毎日ね」
背筋を這い回る悪寒に気づかないふりをして、ぼくはカップを手に取った。手が震え、力が抜けてカップが滑り落ちる。赤い紅茶を浴び、床にぶちまける。なめらかなカップが耳を劈いて、割れる。
「……それで、最後に母さんは言うんだ。お前のせいだって。人殺しはお前だ、この人殺し。この人殺し、ってね」
殴打の音が頭に響く。バラバラに砕け散った破片。狂気は、際限なく膨らみ、爆発する。行き場のないそのエネルギーが、肉を打ち、骨を砕く。
「そうやって母さんがぼくを呼んでるのさ……」
回廊のどこかで、何かが、壁を引っ掻いている。
「でもぼくは、言葉が出てこなくなった。それまでずいぶん、色々なことを言ったよ。慰めたり、謝ってみたりね。でも、そのうち、何も言えなくなっていった。言葉が消えていくんだ。何を言えばいいのか分からなくなって、頭の中で縺れて、喉がつかえて、どれも選べなくて、息ができなくなる。そのうち、言おうとするのも辞めたんだ」
カガシャは聞いている。
「気づいたんだよ、そもそも、母さんはぼくの言葉、聞いてないってことにね。思い出せないくらい沢山の事を、ありとあらゆることを言ったんだ、毎日それなりに、頭を悩ませてね。でも母さんは聞いてない、何も聞こえてなかったんだ。それで母さんはぼくを呼び続ける、この人殺し、ってね」
ぼくは暗い回廊を歩いている。
「ねぇカガシャ……、悪夢はどこにあるんだろうね? ぼくの頭の中には、兄さんの首吊り死体がぶら下がってるのさ。何十、何百、何千のね。母さんが、ぼくを人殺しって呼ぶたびに、その数が増えていった、もう、数えきれないよ」
長い長い回廊が、暗闇の奥へ続く。
赤い蛇の舌が覗く。蜘蛛が這う。ぼくは見ている。
「でも……実際、母さんは正しかった。……ぼくのせいさ、ぼくが殺したんだ」
地下回廊の壁から、赤黒い液体が染み出してくる。生臭い匂いがむせ返りそうなほど充満する。
「たしかに……ぼくが殺した。真っ赤になった目が、ぼくを見てる。人殺し、ってね」
どろどろに腐った血が、回廊を満たす。足首、膝、腿へと上がってくる。目が眩む。ランタンの明かりが消える。暗闇に閉ざされる。
血の匂いと、首吊り死体が埋め尽くす。
「ラトス、それで頼みってなんだい?」
パッ、と、光る。
紅茶の水面に映った天井の明かりが、ぼくの顔を照らしている。
「頼み……?」
明るい部屋は静かで、カガシャがぼくを待っていた。狭い部屋の、壁一面の本棚を眺めた。ジャスミンかなにかがかすかに部屋に香っていた。
「カガシャが呼んだから来たんだ」
紅茶を一口のんだ。血の味がした。
カガシャは笑っていた。
「いや、僕は呼んでなんかないよ」
ぼくは顔を上げる。完璧な笑顔が張り付いたように、ぼくを見ていた。
「そうだっけ、じゃあ、ぼくが間違えたんだ」
ぼくはカップを置いた。
椅子から立ち上がり、ぼくはカガシャに背を向けた。ドアノブに手をかけようとして、そこに絡みつく蛇が、牙を剥いて、蜘蛛を喰うのを見た。
蜘蛛が呑まれる。蛇が地面に落ちる。
「……間違えた?」
無意識に呟いた。
「間違えてなんかいないよ、ラトス」
点滅する。
のたうつ蛇のうろこがぎらぎらと光る。僕は見下ろす。
ゆっくりと、言葉を拾い上げる。
「ああ、そうだね……間違えてなんかいない」
部屋中に張り巡らされた蜘蛛の糸が、蛇を捉え、縛る。喰われるのは最初から、蛇の方だった。
ぼくは思い出し、再び振り向いた。
「そうだ……だって憎かった。ずっと……兄さんが憎くて、邪魔だった」
歪む、廻る。
ぼくは椅子の上に立っている。
回廊の奥、地下室の行き止まり、粘つく蜘蛛の糸が首筋を締め付ける。
「なにも間違ってなんかない。死んで欲しかった」
いつも何でもできて、完璧で、母さんや、他のみんなにいつも愛される兄さんが大嫌いで、憎くて、殺したくて、邪魔で、死んで欲しくてたまらなかった。
「……なのに、兄さんは」
顔が歪むのはいつもぼくの方だ。亀裂が走る。血が滴る。赤なのか青なのか、地下なのか空の上なのか、此処がどこだからわからない。葉のない木々の森、その一本一本が呼んでいる。不自然に長く伸びた枝が、ぼくの方を向いている。
「それで?」
カガシャはカップを傾ける。ぼくを見上げて、見下ろして、ぼくに尋ねる。
「それで……」
ぼくは視線を彷徨わせる。
「……ぼくは……何も言えなくなった。本当は、ずっと聞いていたけど、もうそれを示せなくなった。そうしたら、母さんもだんだん、何も言わなくなっていった」
母さんもぼくと同じように、話すのをやめた。母さんはまたぼくを忘れてしまったかのように、毎日染みついた壁を爪で引っ掻くだけになった。爪が剥がれて血だらけになっても。ガリ、ガリと壁を搔く音だけが、母さんの言葉になった。人殺し。人殺し。人殺し。ぼくを呼んでいる声。それでも、そうやって、呼んでくれることですら……。
「ある日、真夜中に目が覚めたら、母さんがぼくを見下ろしていたんだ。久しぶりに母さんがぼくの部屋に来てくれて、目が合って。嬉しかったよ」
ぼくは口元が綻ぶのを感じていた。それと同時に、ずたずたに胸を引き裂く激痛があった。ひとつひとつの感情に、どんな名前がつけられていたのか、もうぼくには思い出せない。残された言葉は、もう僅かだった。
「ああ、そうだ……兄さんにだけは、いつも……話せたんだ、何でもね」
地の底、黴びた血の匂いに満ちる回廊の奥に、暗闇が待っている。かつてそこに満ちていた光の全てを破壊したのは、自分の言葉だったことを思い出す。
ぼくが言葉を失って、この地の底へ落ちたのは、その罰のような気がした。
「ねぇ、兄さん、なんで死んだの?」
その目が見下ろす。赤い眼が見ている。腐り溶けた亡霊が、微笑んだように見える。
「忘れたのか? ラトス……」
「忘れてなんかない、ただ聞きたいんだ」
兄さんはいつも、いつも必ず、ぼくにこたえてくれる。
笑いかけて、どんな言葉にでも。
「お前が望んだからさ」
すべての音は止んで、最後の灯りが消えた。
永い悪夢がようやく、終わりを迎えようとしている。
「それなら……ぼくたちは人殺しの兄弟だね、カガシャ」
手を伸ばした。
暗い回廊の底へ、繋いだ手と、この星の引力が導いてくれる。
――



