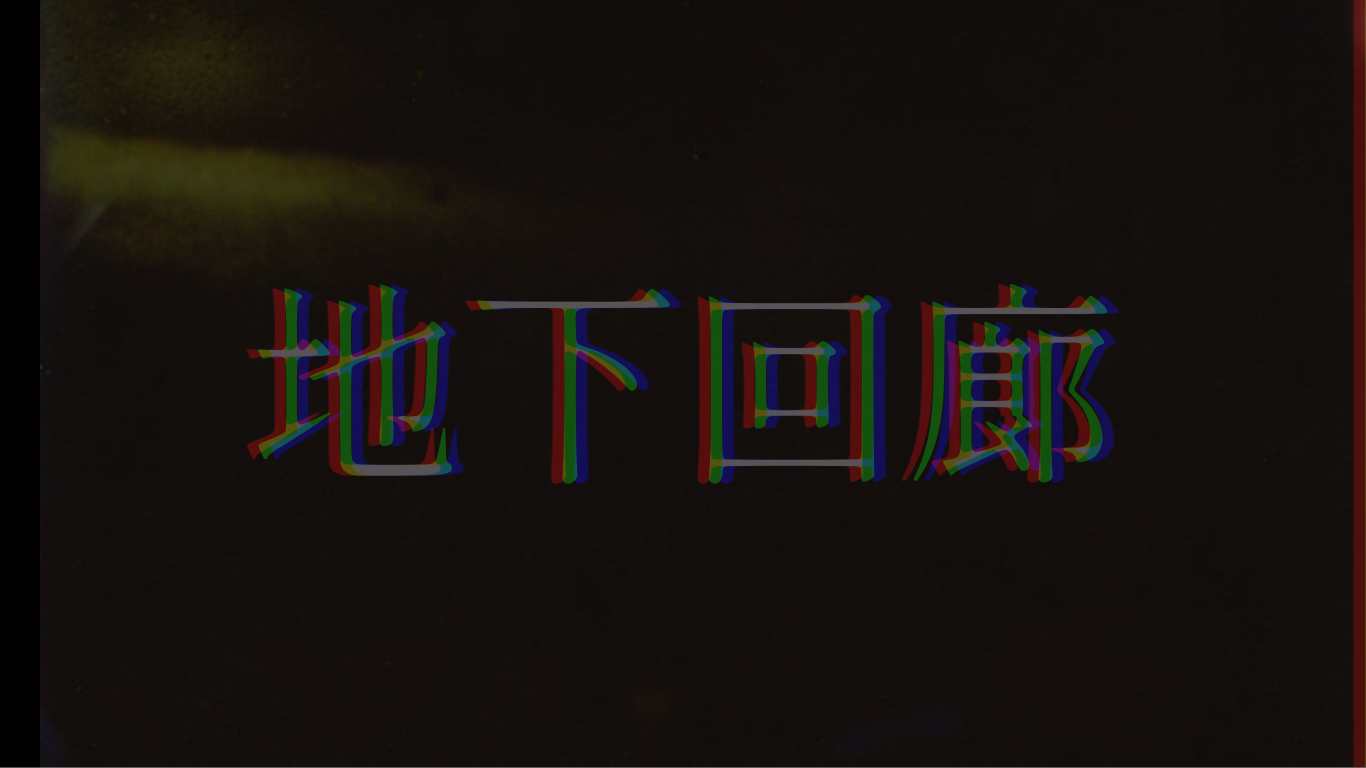赤光

一人の男が歩いている。
彼は、人殺しだ。
何人も殺した。その数も、顔も覚えていなかった。家族を殺したし、そうでないものも殺した。彼が歩きながら感じていたのは、息も詰まるような憎しみだった。
「みんな、死んじまえ……」
男は呟きながら歩いた。薄汚れたジャンパーの裾に黒く乾燥した血がこびりついていた。
どこからか遠く離れたところで、パトカーのサイレンが鳴り響いていた。信号が変わった。男は赤信号の間に、既に横断歩道を半ばまで歩いていた。クラクションが鳴った。
「煩せぇな……」
男は耳を塞いで歩いた。道路の反対から、はしゃいで走ってきた小学生のうち一人が、ドンッと男にぶつかった。
「あっ……ごめんなさい」
そう呟いて脇を抜けていく子どもが、突然、耐えられないほど憎らしく思えた。思いっきり殴りたいという衝動が男の体を突き動かした。
しかし、子ども達は既に走り去っていた。わざわざ追いかけるのは酷く億劫で、その気にはならなかった。遠のくランドセルから、クレヨンの箱が覗いていた。男は舌打ちし、頭を振りながら向き直るとまた歩き出した。
通り過ぎていく街路樹の下で、人が集まって、募金を呼びかけていた。生き生きと張り切った声が、街によく通っていた。可哀想な子どもたちを助けましょう……協力お願いします!……。男には耳障りだった。何人か足を止めるのを視界の端で無意識にとどめ、舌打ちしていた。
《偽善者が》
男は俯いて歩いた。何も見たくなかった。ぼんやりと霞がかった頭のなかを支配するのは憎悪ばかりで、その炎が何もかもを焼いていた。
その時、道の脇に死んだように転がっていた老人の脚に躓くと、男はバランスを崩して地面に転んだ。うめき声がした。
「邪魔なんだよ!」
男は叫んで立ち上がると、老人を蹴飛ばした。うぅ、と頭を守るように蹲る老人の下にはしみだらけの煤けた段ボールが敷かれていた。男は何度も執拗に蹴り上げた。その薄汚い老人が気に食わなかった。他人の施しで生きている、あんな奴らの施しを生きてのうのうと生きていることが憎らしかった。どれだけ蹴っても気が収まらず、何度も何度も踵を振り下ろした。
「おい、殺す気か!……」
神経質な小さい声が男の背後から聞こえた。
男が動きを止めて振り向くと、道の反対側にスーツ姿の男が立っていた。目が合うと、そそくさと歩き去っていった。何度もちらちらと振り返りながら。
「殺す気……? なわけが、ねぇだろ……」
《こんなやつ、生きてすらないんだ》と男は思った。《お前だって、そう思ってるくせに》足早に去っていく背中を睨みつけた。
老人は気を失っていた。血が段ボールに小さな赤いしみを作っていた。
男はふいに、漂う異臭に気付いた。自分がこんな老人の前に立ち止まっていることすら、忌々しく思え、舌打ちをするとまた歩き出した。
鳩が道の脇へ飛び退いた。
《生きてる価値がない。その証拠に、誰も助けない》
男は激しい苛立ちの炎の中で、そう呟いた。
どこかで鴉が鳴いた。
もしも地獄があるなら、それはこの世界だし、もしも自分が罰されるのなら、それはまさにこの人生だったと男は思っていた。そう思うしかなかった。
彼にとって、愛は神話であり、幸福は偽物だった。
男は誰のことも愛したことがなかったし、誰からも、ほんの一瞬たりとも愛されなかった。少なくともそう思っていた。
男は家族を殺した。親を殺した。そうでない人間も殺した。人はそう簡単には死ななかったが、それでもやっぱり、簡単に死んだ。
殺したかった。皆殺しにしてやりたかった。
男は顔を上げた。雲が流れて太陽が覗き、西日が目を貫いた。たそがれの空が澄んでいた。鴉が横切っていった。何もかもが憎しみの炎にゆらめいた。太陽が憎い、空が憎い。後ろから風が吹いた。風が憎い。視線の先に、古びたビルがあった。非常階段が屋上まで取り付いているのを見た。
風に乗って、パトカーのサイレンの音が男の耳に届いた。ずっと聞こえていた。始めて人を殺したときから、いや、もっと前から、ずっと。鳴り出した踏切の警報がかき消した。《行こう》と男は思った。
黄昏の街を歩いた。
すれ違う人々の姿が視界で揺らいだ。《あいつら、生きるために歩いていやがる》蜃気楼のように、笑い声が耳を劈いた。《全部殺したい》轟音を立てて、電車が線路を走り去った。《あいつら全部だ》子ども達が駆け抜けていった。《この世の全てだ》笑顔が、神話が、偽物が、端から端まで、溢れている。
《全部、なくなればいい》
クレヨンで塗りつぶす。力を込めすぎて、ボキッと折れる。
捨てられた絵の事を思い出した。昔、少年だった頃、彼は赤色が一番好きだった。
《なにもかも、全部》
憎しみは地獄の業火の如く、頭の中を焼き続ける。今はもう、好きなものなんて、何一つなかった。
《消えてしまえばいい》
《こんな世界》
そして――
《こんな自分!》
男は立ち止まった。
ビルは眼の前だった。西日は遮られて、周囲には暗い影が落ちていた。
非常階段の前で、幼い女の子が、座り込んで泣いていた。膝が擦りむけて血が滲んでいた。転んだのだろうと男は思った。少女は、薄汚れたワンピース一枚で、髪も泥で汚れていた。
「邪魔だ……」
男は呟いた。少女はハッと気がついて男の方に顔を向けた。潤んだ目が瞬くと、真っ赤になった頬を涙が滑り落ちた。
その瞬間、男の胸の奥に油でも注いだかのように、激しい憎悪の炎が一層燃え盛った。《どいつもこいつも、死ねばいい!》
男は手を伸ばした。
少女の目が見開かれる。
「え……」
男は少女の腕を引っ張り上げ、立たせた。
「行け」
少女は驚いたように男を見上げた。少女は、痛みも忘れたのか、ただ目を瞬かせていた。不思議そうに、何かを尋ねようとでもしたのか、唇が震えた。
「あっちへ行け」
低く呟くと男は、自分が歩いて来た背後を指さしてから、非常階段の錆びついたチェーンをくぐり、階段を登り始めた。足元がふらついていた。
「あのっ……!」
踊り場のあたりで下から呼び止める声が聞こえ、男は振り向いた。
「ありがとう……」
少女は涙を拭い、泥だらけの頬で、男の目を見上げて微笑みかけた。
男はまた階段を上り始めた。それから、もう二度と下には目を向けなかった。
少女は歩き出した。
サイレンが響く。
燃えるような夕焼けが、空を満たし、やがて、消えた。