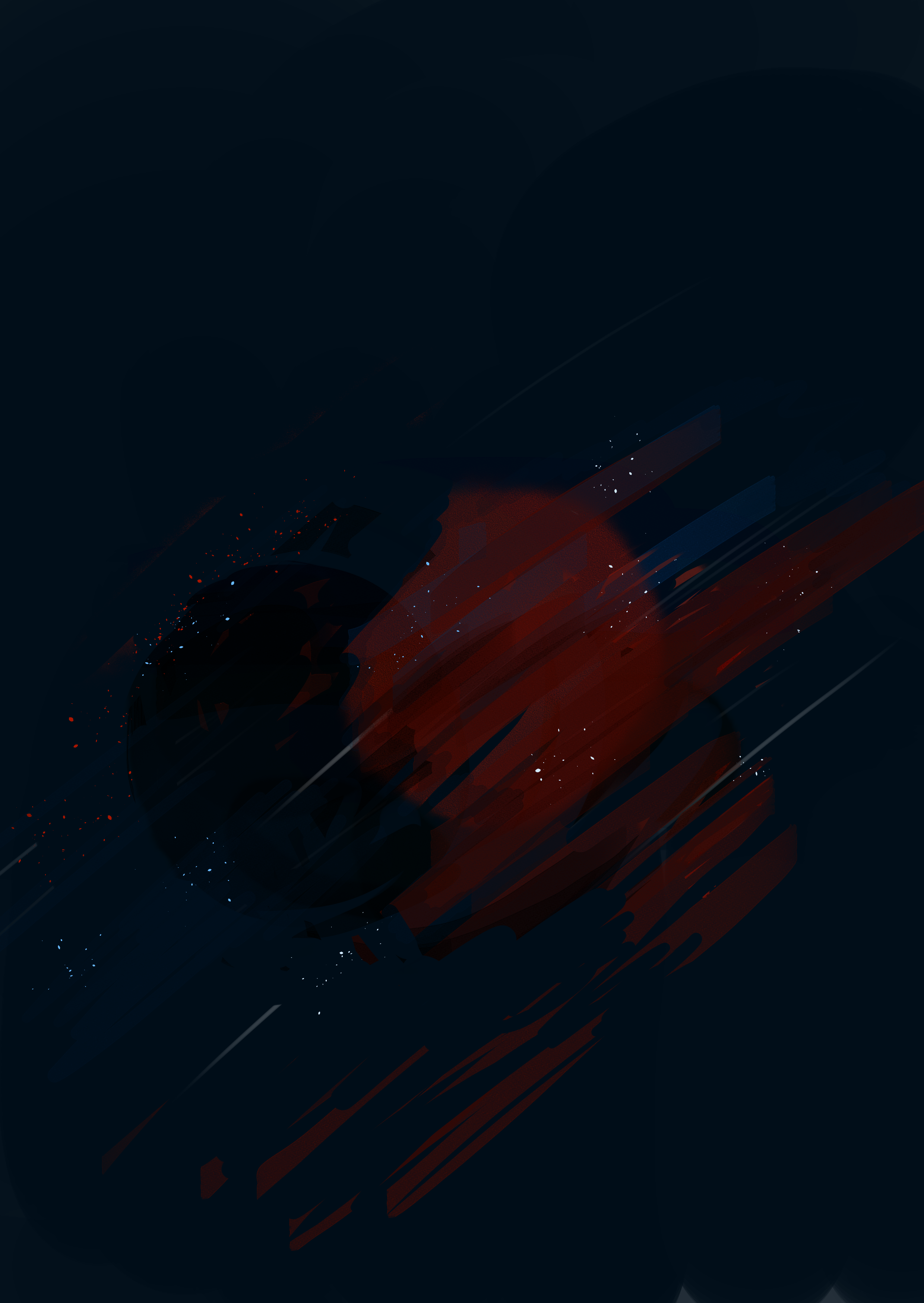無知の知の困難、無知を諦める。

無知の知
かの有名な古代ギリシャの哲学者、ソクラテスの考え方として、最も有名なのは「無知の知」ではないだろうか。
この言葉が基本的に意味するのは、本当に賢い人は自分が無知であることを知っているものだ、という事である。
とてもわかりやすくシンプルであり、最もらしい。だが、その実践は果たして簡単なことだろうか。この無知の知と言う言葉を聞いて、自分が無知である事くらい、よく知っているさ、と思う人も多いだろう。そうか、無知を自覚することが大事なのかと、それで無知を知った気になることは簡単である。だが私なんかの場合、よく考えてみると、無知の知、この実践が如何に難しいかということを、ひしひしと感じざるを得ない。
知る
そもそも「知る」とは何か、これも哲学的には数多の論争がある。無知を知る、これは一種のパラドックスに陥りかねない。自分が無知であることを知ったとしたら、その場合、無知の知が達成できているのだろうか。無知を知った気になっているだけではないのだろうか。この状態こそ、無知の知が否定する知ったかぶりの勘違いそのものなのではないだろうか?
だとすれば、無知の知は論理的に矛盾した言葉遊びに過ぎない、不毛な概念なのか。
無知の知は、論理的な問題ではなく、より感覚的な問題なのように思われる。
あなたは自分を無知だと思いますか? という問いに自信満々で頷いたとしても、案外、人間は自分が思っている以上にはるかに無知なのだ。この世界のことなど、ほとんど何も知らないに等しい。他人が何を考えているか知っているだろうか。あるいは、この世界がいくつの原子で構成されているか知っているだろうか。光や、色や、音とはなんだろうか。死んだらどうなるだろうか。おいしい料理はなぜおいしいのか。隣の教室でどんな授業が行われていたのか。このようにして、知らない、知り得ないことについて、無限に述べることができる。だとすれば、私達には知っていることは何もないようなものだ。それなのに、自分はそれほどまでに何も知らないと実感しているだろうか?
正体のわからない、得体のしれないものに人間は不安を感じるものだ。だが健康的な精神の人間なら、ある程度安定した自分の生活の中で、そういった無知の不安に駆られ続けることはない。
知る、ということは、ある不確定なものごとについて、自分の中に確定した枠組みを与えることだ。
生物の生存に必要不可欠なのは、真理ではない。善や正義ではない。人間であれど、何一つ真実のない幻の中を生きられる。生物は限られた世界の中で物事を知り、そこで生きて、死んでいく。生存とはせいぜいそれだけのことである。ついでに子孫が残せれば、それが適応ということであるにすぎない。
人間の真理
生命と究極の真理は相反するものだ。人間が生きている限り、究極の真理を知ることができないだろう。知ることこそが真理に矛盾する。知るとは、何か不定なものを、自分の視点から意味づけ、自らのうちにつくりだすという行為である。人間はいつも無限の海から、手の中に入り切るだけのものをすくい取るようにして、手製の瓶に詰めていくことしかできないのだ。
だが少なくとも、より科学的で、より論理的なものを知っていくことはできる。地球が太陽の周りを廻るのか、太陽が地球の周りを廻るのか、そのどちらを知っていたとしても、人間が生きて死んでいくことを妨げない。むしろそんなことを気にもかけず、問うことがなくてもいい。だが、科学という手法で、そのどちらが「より科学的であるか」を判断することができる。
では科学を突き詰めれば真理に辿り着けるのだろうか。科学があらゆる問いに答え、あらゆる問題を解決し、宇宙の力や時間、生命、素粒子の動きを支配した時、科学は真理と等値になるのだろうか。つまり、科学の行き着く先があるとしたら、それを真理と呼ぶことができるのだろうか。
ある意味ではそれも間違ってはいないのかも知れない。しかし、本来の順序は逆だったはずだ。真理を追求するための手法として洗練されてきたものが、哲学であり、科学であったのではないだろうか。そもそも、真理とはいったいなんであるか。
結局行き当たるのは、いずれの場合にせよ、真理は幻想であるということである。世界の究極の真理、それが世界には存在していると仮定しよう。しかしそれを人間は手に入れることはできないだろう。人間が手にすることができるのは人間の真理にすぎない。それは常に不完全で有限的で、曖昧な真理だろう。人間は真理にたどり着くことが出来ない。究極的に「知る」ということはできない。
だからすべてが無意味なのか? 真理など幻想であり、一生手に入らないそれを追い求めることは愚か者の行為か? まぁ、そうなのかもしれない。だが、愚かでもいいじゃないか? 私はそう言いたい。
先ほど、生物に真理は必要不可欠ではないと書いた。でも、心にはどうだろうか。心にはさまざまなかたちがある。私たちは生きている。私たちは人間であることから逃れられない。心から逃れられない。だから、私たちには人間の真理が必要なこともある。それが究極の真理ではないとしても。
無知の不安
知らないものに直面すると、人間は不安になる。木の陰から物音がした。一体何がいるのだろう。だから知ろうとし、勇気を出して木の裏を覗き込む。そこには一匹のリスがいる。ああ、なんだ、リスか。とほっとして、人間は安心する。人間の生とは、この繰り返しである。
だが人によって、無知の不安の射程や性質は異なる。「気になる」事柄が違うのだ。この森に木々は何本あるか、この木は何年前から生えているか。それが気になる人がいる。あるいは何匹のリスがいるか、そのリスはなにを食べているか、どこからきたのか。森の向こうになにがあるか、海や、空の向こうになにがあるか。それを知らなければ気がすまない人もいる。
無知の不安は、好奇心によって解決される。人間は船を作り、海を渡る。顕微鏡を覗き、万物の根源を探る。望遠鏡を覗き、ロケットを作り、宇宙の果てを知ろうとする。
ダーウィン的な適応の進化論を採用するなら、人間という生物の遺伝子は、どのような適応により子孫を残してきたか。それは無数にあるだろう。その一部として、無知への不安、好奇心、そして勇気をあげても、大げさではないはずだ。
そしてその「無知の不安」の差異こそが、複雑な人間世界を作り上げるに至ったのだろう。人間は、知りたいことを知り続ける。死ぬまで満足しないことも多々ある。そもそも知ろうと思わないことについて、人間は無知を自覚しない。ただ、知りたいと思うことについてのみ、無知を自覚するのである。
無知の無視
このように考えた時、果たして無知の知とはどのように実践可能なのか。それを意図的に行おうとしてもあまり成果は得られなさそうである。そもそも無知自体は、自明なことである。そんな事は、どんな愚かな人だって知っている。私たちが、何を知っているというのか。知らないことは当たり前である誰もが何も知らない。そして問題は、そうであるにも関わらず、無知であることを感覚のレベルでは無視している、ところに生じるのではないかと私は考えている。
自分が通勤に使う電車があるとする。その路線は、1日に何本あるのだろうか。その時刻全てを、覚える必要があるかというと、別にない。自分はいつも決まった時間にやってくる電車に乗り、決まった時間に到着する駅に降りるだけだ。その行為に、電車の型番や、車両や座席の数、路線の本数を知る必要はない。人間にとって、こういった無知は、気にする必要がない。それを知っていても知らなくても変わらないのだから、無知として認識されない。そういった人に、電車を知っていますか? と問えば、知っている、と答えるだろう。人間にとって、知るとはそういうことだ。しかし、鉄道が好きな人の中にとって、その無知は我慢ならない。そこで、無知は気にかける必要のある、有意味なものになるのだ。
こう考えてみると、「知る」ことも「無知」も、とても人間的だ。人間的ということは、曖昧で、矛盾して、わざとらしいということだ。
知と無知
知る以上、無知からは逃れられない。「知る」ということは、知っていることと知らないことの間に線を引き、知らないことについては無視することだ。そうすることで初めて、人間は何かを知ることができるのである。
無知の知とは、「私は何も知らない」と「知る」ことだ。それは可能であるか。可能かもしれない。然しその場合、何かを語ることができるだろうか。何かを為すことができるだろうか。本当に何も知らない人間に、なにができるだろうか?
生きていれば人間には知らねばならない時が来る。
そうして人間は、無知を諦める事になるのである。