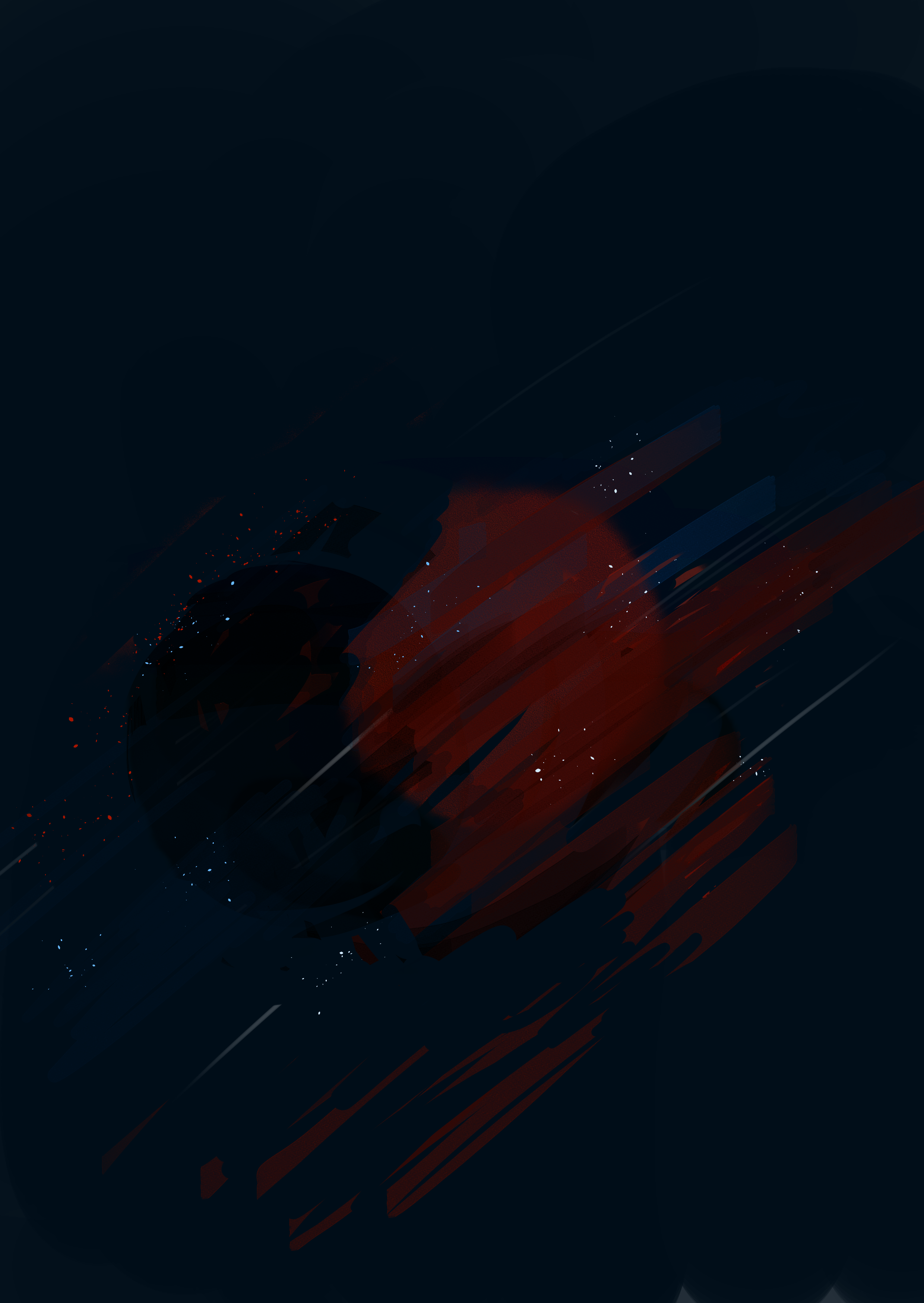「生きるか死ぬか」は、くだらない問題なのか。

to be or not to be.
William Shakespeare「Hamlet」
意味と理由
大学三年生の秋、カウンセラーの先生と、生きる意味や生まれてきた理由について話し合ったことがある。半年ほど前のことだ。
ぼくはその頃、両親のことで悩んでいた。自分は生まれてこないほうが良かったと思っていた。この先も生きていきたいと思えなかった。日々が苦しく、夜は眠れず、授業に出ることもできない。
生きるか、死ぬか、ぼくにはすくなくともそれが問題だった。そして答えは出なかった。ずっと死にたかったし、でも死ぬことはできなかったからだ。
先生と話していて、生きるか死ぬか、なんて下らない問題なのだろうか、とも思った。生まれた意味、生きていく意味、そんな事はいくら考えたってわからない、答えのないことだ、と先生は言った。考えても仕方のないことだ、と。
生きるか死ぬか、などと悶々と悩んで地面ばかり見ているのは、愚かな行為か、それは愚かな問いか、何の意味もない、下らない迷いなのか。
本当にそうなのか。
ぼくは結局、カウンセラーの先生とあまり良い関係を築くことができなかった。先生は時間をかけてくれたのに、ぼくは途中で駄目にしてしまった。それを申し訳なく思う。だけどあの時に話し合ったことについて、繰り返し考えていくことが、せめてぼくにできることだと思っている。
生きるか死ぬかなんて、究極的な事を突き詰めてもしょうがない、と先生は言った。
だけど結局、ぼくはそれを問わずして生きていくことはできないだろう。
死に囚われる
死にたい、と本気で思った最初は、記憶にある限り、中学生の時だった。ぼくとしては、一度でも、それなりに心から死にたいと思った人間にとっては、生きるか死ぬか、ということは、人生の根本問題になるのだろうと思っている。それを忘れ去ることもあるだろう。でもそれはまたやってくる。生きるか、死ぬか。今すぐ死ぬか、明日まで生きるか。
とはいえ、それが頭の片隅にある程度ならまだしも、その問いが頭の中をいっぱいに埋め尽くしてしまうと、途端に生きることが不可能に近くなる。食べたり、寝たり、起きたりすることすら苦痛になる。明日のことすら考えられず、何年も先のことなんて考えようとするだけで目の前が真っ暗になる。死にたくなる。そして死が満ちる。視界の一面が、死に埋め尽くされる。生きることなど、考えられなくなる。
だから先生は、問わなくても良いのではないか、という視点を投げかけてくれたのだと思う。あの時のぼくはそれを受け入れなかった。それでも、どうしてもぼくは、意味が欲しかったからだ。生きていていい理由、生まれてきてよかったと思えるなにか。ありもしないものが欲しくて、諦めきれなくて、馬鹿馬鹿しくもがいていた。
そんなものはない。
誰かを憎む必要もない。
憎しみと春
大学三年生が終わった。春が訪れようとしている、まだ冷え切った三月、地元に帰ってきて、なぜかとても、心は穏やかだった。この三年間のほとんどは、激しい苦痛と憂鬱に満ち、日記に残されているのは傷ついた時間ばかりだ。だが今はなぜか、静かで、満ち足りている。
いま、何も望んでいない事に気づいたからかもしれない。
両親や家族への憎しみに駆られた時もあった。怒りが消えず、憎くてたまらなかった。復讐心に駆られ、自らの死を突きつけたくて仕方がなかった。それができない事に苦しんだ。けれどもぼくが考え続けたのは、ぼくが本当に望んでいることは何なのか、ということだった。
本当に望むことが復讐や仕返しなら、それをしても良いはずだ。これは現時点でのぼくの意見だが、【本当に】望むなら、どんな罪も犯すに値すると思う。この世界で、ぼくらを制限するのは、物理法則だけだ。可能なことは、あくまで可能であり、してはいけないことはない。【本当に】自殺を望むなら、それはしても良いことなのだし、【本当に】誰かを殺したいなら、そうするしかない。
だがこの国にも法律があり、違反すれば刑が課せられる。その約束の中でぼくたちは数々の「罪人」を罰してきた。ぼくらには人として、罪を犯す権利がある。そしてその場合には罰を引き受けることが、人としては誠実なのかもしれない。でも必ずしもそうしなければならない義務もない。
望むこと
結局は、自分が何を望むか、ということから人は逃れられないし、他者からそれを奪い取ることも出来ない。心は各々のものでしかなく、それは他の人のものにはならない。それだけのことなのだ。
ぼくはほかの全ての生き物と同じように、生まれた場所で、望むことのために選択することができる。それなら自分の命を、ぼくを傷つけたひとたちを傷つけるために使うのか。死んで、憎らしい人たちを後悔させたいのか、その人達の人生を徹底的に傷つけて、それで満足なのか、ぼくが本当にしたいのは、そんなことなのか。
ぼくの場合、やっぱりそれは違った。
憎む気持ちが確かにあるとしても、それだけではなかった。傷ついたことだけではなかった、今は失われてしまったとしても、ぼく自身が愛している思い出があり、だからこそ憎しみもまた、ここにあったのだ。
他者が問題なのではなかった。ぼくの場合は、ぼくの心の弱さだった。ぼくは誰も憎む必要がなかった事に気付いた。ぼくは自分が変わるために全力を尽くすべきであると分かった。
憎しみに行動を託すことはぼくの本当の望みではなかったのだ。ぼくの望みは、少なくとも幸福だった。家族や人々が幸福でいることだった。愛しい思い出が一つでも多く、わたしたちの中にあることだった。それは叶わないかもしれない。でも叶わないからといって憎んではならなかったのだろう。
雪解けと花
気がつくとぼくは、生きるか死ぬか、その問いにある程度、落ち着いて向き合うことができるようになった。本当に望むときがくれば、ぼくは死ぬ事を選ぶだろう。そうしたいと思う。でも今、ぼくはまだ少し、生きてやりたいことがある。まだ、ぼくには傷つけたくないものがある。どんなに些細なものでも、まだ、踏みにじりたくはないと思うものがある。
どんなに強い憎しみが心を焼いても、守りたいものがあるのだ。どんなに恐ろしいものに追われていても、小さな花を踏みにじらずにいたいと思う。それだけの強さがほしい。ぼくが本当に望むのは、そういうことだった。
雪が溶けるように、ぼくはいつの間にかこの心から憎しみが消えていることに気づく。ぼくはたくさん傷ついたが、それでも家族のことが好きだと思うこともある。今は壊れてしまったとしても、決して嘘ではなかった思い出があり、ぼく自身、素直に幸福だったと認めるべき時間がある。
また憎しみは繰り返しやってくるだろう。きっと多くのことは何も変わらない。ぼくには生まれてきて良かったと思える日はこないだろう。ぼくはこれからもぼくのいない世界で、みんなが幸せだった夢をみるだろう。ぼくが生まれてきた世界は、ぼくの好きな人たちが苦しんだ世界だった。みんなが幸せだったなら、ぼくはここにいなかった。それでも尚、自分の存在を愛することなどはできない。それがぼくなりに、他者を愛するということだからだ。
負うこと
誰にも、誰かの存在を否定する権利などありはしない。ぼくは自分の望むことのために今日も、生きることを選ぶ。その責任を負う。ぼくは自分が犯すに値すると思う罪を自らの責任で犯し、その罰を引き受ける。そういう馬鹿げた生き方をぼくは選ぶ。それがぼく自身に必要だからだ。生きるか死ぬか、その問いにぼくなりに答えることが、どうしてもぼくには必要だからだ。
滑稽でも構わないよ。地獄が待っているとしても、悪くないと思っているんだから。
真に重大な哲学上の問題はひとつしかない。自殺ということだ。人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題に答えることなのである。
「シーシュポスの神話」(カミュ 清水徹訳 新潮社 2005.)