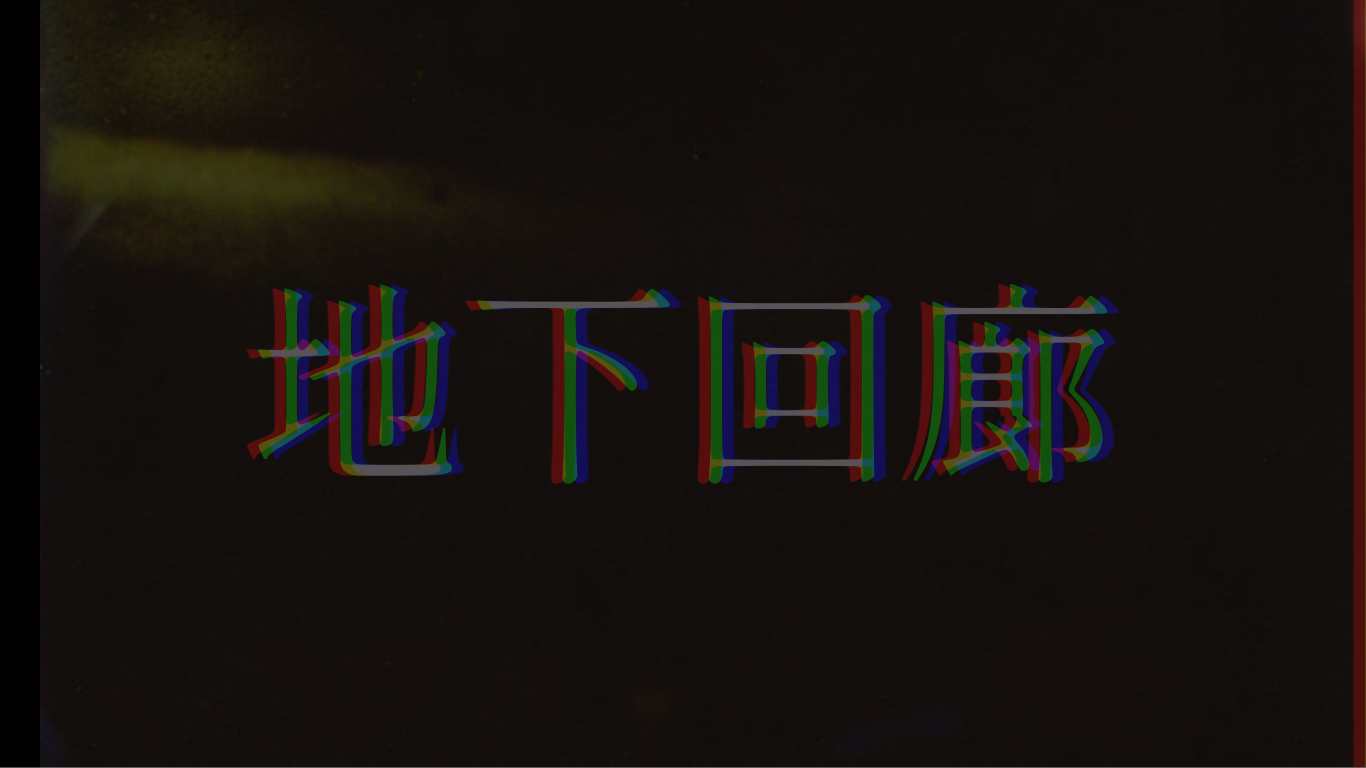きみはユーレイ

ぼくは死んだら、消えてなくなると思ってた。
だからきみに出会ったとき、本当にびっくりした。きみは、ふわふわ空に浮いてて、しかも半透明で、さわろうとするとすり抜けた。
きみはユーレイなの? って聞いたら、きみは首を傾げて、両手を胸の前にぶら下げて、ひゅ〜どろろ、って言って笑った。
*
はじめてきみを見つけた時、青いセーラー服のきみは線路の真ん中に立ってた。立ってたというより浮いてた。踏切がカンカン鳴ってて、バーが下りていて、電車が向かってきてた。
ぼくは最初、ただそこに人が立っているんだとばかり思っていたから、何にも考えず踏切の中に飛び込んで、きみをひっぱろうとした。そしたら手がすりぬけた。踏切の中でぼくはぼんやりきみを見つめた。見上げた半透明の顔に空の青色が透けている。時が止まる。けたたましい音が鳴り響いている。そう、時は止まってない。
ぼくは途方にくれた。
「どうして、泣いてるの?」
きみは優しい大人びた声で、ぼくに聞いた。ぼく? ぼくのことはどうでもよくて。
「大丈夫、見てて」
電車は迫っていた。さわれないきみを引っ張っていくこともできないぼくは、ひとりで線路の反対側に歩いていった。バーをくぐって、そして振り向くとちょうど、巨大な鉄の塊が轟音を連れて走り抜ける。ぼくはギュッと目を閉じて身体をすくませた。
やがて電車の音が遠くへ去っていく。ぼくは恐る恐る目を開ける。
きみは変わらずそこに立ってた。というか浮いてた。
ちょっといたずらっぽく笑うきみには足はなくて、まるで、昔おかあさんに読んでもらった絵本に出てきたおばけみたいだって気づく。
「きみはユーレイなの?」
それが、ぼくが始めてきみに訊いたこと。
良く晴れた春のある日で、風が強くて散った桜の花吹雪が、きみをすり抜けていった。
*
「なんでユーレイには足がないの?」
「きみはどこからきたの?」
「何で透けてるの?」
ぼくはきみに色々訊いたけど、きみはあんまりほんとうのことを教えてくれなかったように思う。というのも、多分きみだってほんとうのことなんか知らなかったんだ。だからきみは、いつもふざけてぼくにデタラメをいった。
「足があると、猫が寄ってくるから」
「地獄から来たんだよ」
「映画館で、後ろの人を邪魔しなくて良いように」
きみはねこが嫌いで、天国が嫌いで、映画館が嫌いだった。きみはぼくの知らないことをたくさん知っていて、ぼくが考えたこともないようなことをたくさん話してくれた。教えてくれたこともある。たとえば、
雨の日に家に入る前、傘の雫はしっかり落とすこと。卵焼きにはマヨネーズを入れたらおいしいこと。リコーダーは家では吹いてはいけないこと。
「ランドセルの中に、ねこは隠しちゃ駄目だよ」
ある日きみは、そんなことも教えてくれた。
「どうして?」
「ねこは鳴くから」
「ねこが鳴いたらだめなの?」
きみはねこが嫌いだった。ぼくはねこが大好きだったから、ねこが嫌いな人もいるんだなあとちょっとおどろいていた。
「リコーダーを吹いたら、ねこが鳴いてもわからないよ」
ぼくはきみのためにリコーダーを吹いてあげた。だけど、きっときみはぼくのために、ぼくのリコーダーをきいてくれていたんだ。だってぼくには、他にだれもリコーダーを吹いてあげられる人がいなかったから。きみはぼくの下手なリコーダーを笑わないで聞いてくれる、たった一人のひとだったから。
*
きみはいつもその踏切に浮かんでいたから、ぼくは毎日、そこできみと話をした。きみがいるのは、学校からの帰り道だけ。それと、雨の日以外。
ふしぎなことに、きみが見えるのはぼくだけみたいだった。たまに踏切を通る人がきみの身体を通り抜けていくとき、ぼくたちは顔を見合わせてクスクス笑った。
「きみはそこから動けないの?」
ジバクレイ、というのを聞いたことがあった。
「足がないからね」
きみはそんなふうに言っていたけど、足の問題なら立っていることもできないのではないかとぼくはひそかに思っていた。きみは多分、ジバクレイというやつで、だとしたらきみはここの踏切で死んでしまったのかもしれない。
でも、そこで事故があった話を聞いたことはなかったし、近くに花束が置かれていることもない。そこは人が死ぬような場所でも、人が死んだ場所でもなさそうに見えた。ただ、電車の道と人の道が交差する場所。道と道の重なるところ。
だけどはじめてきみに会った時、ぼくはよく分かった。その中に立っていたら、人は死んでしまうのだということ。あと、ユーレイはもう死んでるから、大丈夫だってことも。
そうやってきみと話していると夕暮れがやってきて、辺りは薄暗くなっていく。線路の脇の街灯にあかりが灯ると、きみの身体は透けて、光る。
「遅くなる前に、帰らないといけないよ」
きみがそう言うと、ぼくはすこしかなしい気持ちになる。それが、お別れの合図だから。
「……どうして?」
「化け物に襲われてしまうから」
ユーレイのきみがそう言うなら、化け物だって本当にいるのかも知れないと思ったけど、ぼくは家に帰りたくなかった。
「また明日」
でもきみがそう言ってくれると、明日という、未来の扉がひらくような感じがした。真っ暗な未来の、ほんの少し先に光が伸びて。また明日。
「うん、また明日ね」
ぼくは家に帰る。きみと、明日のことを考える。ユーレイ。死んだら消えると思ってた。死んだら全部なくなるって。だからこの痛いのも、怖いのもなくなるって。ぼくはユーレイになりたくなかった。でも、ユーレイになれば、誰にもさわる事はできない。だから殴られたり、叩いたりもされない。そしてユーレイになれば、きみにさわることができるのかな? 手をひっぱって、踏切の中から助けてあげることができるのかな? ああでも、ユーレイなんだから、踏切の中から助けてあげる必要ないんだっけ。そんなことを考える。一日が終わる。
朝がくる。明日がくる。また、きみと話す。お別れをする。また明日、約束をする。ぼくは背が伸びていく。
「きみは、背は伸びないの?」
踏切の脇に捨てられた空き缶を眺める。
「成長するのは、生きてる時だけなんだよ」
きみは髪も伸びないし、きっと爪も伸びない。成長。ぼくはたくさんの言葉を覚え、少しずつ難しい計算もできるようになる。歯が生え変わる。成長。
「じゃあいつか、ぼくはきみの背を追い抜いちゃうのかな」
きみは、どうかな、と笑った。
*
ある雨の降っていた日、ぼくは捨てねこを見つけた。
ミャアミャア鳴いていて、雨で濡れた体が震えていて、ぼくは放っておけなくてそのねこを抱きかかえた。帰り道の踏切に、きみはいなかった。雨の日には、なぜかいつもきみはいない。でも、きみはねこがきらいだから、それで良かったのかもしれない。
ぼくは家にその子を連れて帰った。おかあさんは、捨ててきなさいとすごく怒って、ぼくとねこは追い出されてしまった。傘もなく、ぼくは来た道を辿った。もとのダンボール箱の場所まで来ると、軒下に吹き込む雨がその箱をぐっしょり濡らしていた。
ミャア、ねこはぼくを見上げてか細くないた。ぼくはきみに教えてもらったことを忘れていたわけじゃない。でも、この小さくて濡れて震えているちいさなこねこを、どうやって捨てたらいいのか、他にどうしたら良いのか、わからなかったんだ。
だからぼくは、ねこをランドセルに隠して家に帰った。すててきたよ。と嘘を吐いて。
雨の音と匂いが、隠してくれると信じた。リコーダーは家の中では、吹けないから。ぼくは廊下の隅にランドセルをそっと置く。それから、台所で作る夕飯を、少し取り分けておく。ねこになにをあげたらいいのか分からないから、明日図書館で調べようと思っていた。
そのとき、のどが潰れたような動物の悲鳴が聞こえてきた。ぼくはハッとして庭に向かう。後ろで置きそこねた包丁が床に落ちる音が鳴る。
はげしい雨が降っていた。
お母さんが、ぼくの逆さまのランドセルを手に庭に立っていた。教科書と鉛筆が、散らばって雨に濡れていた。そのなかに、ちいさなぼろ布みたいに落ちている、
ねこ。
潰れたねこ。
尻尾も、耳の先も動かない。もう鳴かない。
おかあさんがゆっくり、ぼくに振り向いた。
どうして嘘をついたの。
ぼくは、ごめんなさい、と謝った。
どうして謝るの。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
泣きながら謝った。泥のなかに頭を突っ込んで謝った。背中が蹴られて、泥の味。
家に引きずり込まれて、扉が閉まると、雨音が遠くくぐもった。
ごめんなさい。ごめんなさい。
ぼくのせいだ。
ぼくが、きみの教えてくれたことを守らなかったからだ。
ごめんなさい。
ぼくのせいで死んでしまったねこ。ぼくが殺してしまったねこ。
どれだけ殴られることも、蹴られることも、それは罰だ、と思った。
*
「きみのせいじゃないんだよ」
次の日、雨は止んでいた。ぼくは、踏切の近くに連れてきたねこを埋めた。それから毎日、お花を供えるのが、日課になった。
「……ちがうよ、ぼくのせいだよ」
お花は、電車がやってくると、風に舞い上がって飛んでいく。
「……ねえ、ねこもユーレイになるのかな?」
ぼくは聞くと、きみは首を傾げた。
「ねこは天国に行くよ」
「……天国」
きみは、地獄から来たなんて言ってたこともあった。けど、ユーレイは未練があってこの世にとどまっているだけで、天国や地獄には、これから行くんじゃないのだろうか。ぼくはちょっとは大きくなって、そんなことを思うようになっていた。
「じゃあ、いつかきみが見つけて、ぼくの代わりに謝ってくれる?」
ぼくがそんなふうに言うと、きみはちょっとびっくりしたような顔をする。
「きみはきっといつか、天国に行くでしょ?」
「……天国には、行けないよ」
「……どうして?」
「天国は好きじゃない」
そっか、きみは天国が嫌いなんだった。でも、なんでだろう。今度はそれを訊いてみると、きみはこう答えた。
「天国はね、優しくて良いことをした人が行く場所なんだよ」
それなら、きみは天国に行けるはずだとぼくは思った。きみはぼくにも優しくしてくれる。とっても良い人だから。
でも、きみは天国が好きじゃない。ぼくはなんと言ったらいいかわからなくなって、結局こう訊いた。
「……きみは、どうしてユーレイなの?」
きみが最後まで答えてくれなかったいくつかの質問のうちの、ひとつがこれだった。
*
ぼくは小学校六年生になった。ランドセルはもうボロボロで、右の肩のところが千切れそうになっていた。
きみと毎日話す。また明日。また明日。それを繋いでいく。
そんなある日ぼくは、町中できみにそっくりの人を見つけた。
凄くびっくりして、ぼくは立ち止まってしまった。きみが線路の外に出て歩き回っているのかと思った。でも違った。その人には足があって、半透明でもなかった。良く見たら顔も、髪の長さも全然違った。同じだったのは着ていた服だった。それは制服だった。青いセーラー服。
「きみの服、あの川の向こうの中学校のと同じなんだね」
ぼくがそう言うと、きみはちょっと面白そうな顔をした。
「探偵みたいだね」
「ぼく、やっぱり気になるんだよ」
踏切のそばに、コスモスを供える。飛んでいかないようにぼくは石を置く。
「きみがだれなのか、とか。いつ死んじゃったのか、とか」
きみはなんだか楽しそうに聞いていた。ぼくとしては、探偵ごっこのつもりではなくて、ほんとうに気になるのだけれど。
「でもきみは教えてくれない」
ぼくは少しずつ背が伸びていた。きみと目線の高さが近づいていく。
「べつに、どうでもいいことじゃないかな」
「まぁ、そうかもしれないけど……」
きみのその制服。その中学校に行けば、何かわかるだろうか。その学校に死んだ生徒がいるか、調べてみたけれど新聞やテレビの報道は見つからなかったのだ。
ぼくは、知りたかった。
例えば、ユーレイが天国にいける方法とか。
死んだら消えてなくなると思ってた。でもそうじゃないらしい。だとすれば、死後の世界、天国みたいなところも、あるんじゃないか。きみはそこへ行けず、何か未練があって、こんな場所に縛られているのではないか。ぼくはだんだんそう思うようになっていった。
でもぼくがどれだけの質問をしても、注意深く話を聞いても、ぼくには何もわからなかった。例えばきみの未練とか、そういうもの。
ただわかるのは、きみはぼくにとても優しい言葉をくれる、唯一の人だということだけだった。
そうして、ぼくは中学生になった。
桜の季節、新しい制服に身を包むぼくに、きみだけがおめでとうと言ってくれた。
*
また明日。
だけど雨の日には、「また明日」は途切れる。ある日、いつものようにきみと話していたら、途中で雨が降り出した。するときみは瞬きのうちに消えてしまう。それはもしかしたらヒントかもしれないと思った。ぼくは、その日、踏切の周りを念入りに調べてみた。
でも、手がかりのようなものは何もない。そのうちぼくは踏切の中心に立って、鉛色の雨空を見上げていた。
カンカン、と踏切の警音が鳴り響く。ぼくはなぜかそこに立ち尽くしたまま、ぼんやりとその音が脳内に反響するのを聞いていた。
きみがいない。すべてが、半透明の幻のような気がしてくる。
ぼくはずっと独りで、ここに立っている。
ここに、ずっと。
思考を引き裂く汽笛の音が、ぼくを連れ戻す。ぼくは我に返ると踏切から外へ駆け出した。
背後から轟音が襲う。
振り向くと、薄暗い空の下、煌々と輝く電車が走り抜ける。
きみのいないこの場所は、とても恐ろしいところのような気がして、ぼくは弾かれたように踵を返して走った。でも帰るところもなくて、あてもなく、疲れるとゆっくり歩いた。
家には帰れない。そこにぼくの居場所はない。
その頃、おかあさんはぼくの知らない人と急に再婚した。そのひととはあまり話したこともないけれどなぜかその目つきがとても怖かった。ぼくはおかあさんにますます嫌われていく。ぼくはいつも邪魔者だった。
やがてたどり着いた公園で、キィキィ、古びたブランコを漕ぐ。雨が降っている。
*
晴れの日には、またきみに会える。
「その怪我、どうしたの」
きみは少し悲しそうな顔でぼくに訊いた。
「あぁ、これ学校で、やられたの」
いつの間にか、家だけじゃなくて学校も、ぼくの戦場になっていた。
「いつも奇跡みたいにハズレくじを引いてるね」
「昔っからそう。きみは運が良いほう?」
と聞くと、きみは吹き出した。
「運がよかったら多分、こんなことにならないよ」
半透明な両手を広げるきみも、なんとなくぼくに似てるような気がして、ちょっと笑った。ほっぺの痣が痛い。
ぼくはその頃、きみとよく映画の話をした。きみは映画にとても詳しくて、ぼくがテレビなんかで見た映画の話をすると、きみはどれも見たことがあると言う。きみはこの世のすべての映画を見たことがあるんじゃないかと思ってしまうくらいだった。お小遣いなんて貰えないけど、食費は貰っていたから、少しずつ貯めて、ぼくはたまに映画館に行くようになった。
ある日、その帰りに、後ろから突然だれかに蹴飛ばされた。ほぼ満席の映画館で、ぼくの後ろに座っていた、クラスメイトだった。ぼくが邪魔だったって。
きみみたいに透けてるユーレイなら邪魔にならなかったかも。なんてその時考えて、きみが昔言ってた冗談を思い出して少し愉快な気持ちになった。
ぼくは虐められるようになった。
小学生の頃も、汚いとか、喋り方が変とか、からかわれることはあったけど、その比じゃなかった。ただそこにいるだけで、蹴られる。暴言を吐かれる。なぜなら、王様がそう決めたから。王様の言うことは絶対なんだ。ぼくがなにか言うとみんな馬鹿にして笑う。それから死ねと言われる。開け放した窓を指さしてわらっている。
みんな、ぼくに死んでほしいみたいだ。おかあさんも、たまにぼくに死ねと言う。ぼくは生きていてはいけないのかもしれない。
「死ねって、どういう意味なのかなぁ」
ぼくはきみにそう尋ねた。自殺しろという意味なのか。それとも、ぼくがここにいることを責めているのか。ただ傷つけるだけの意味しかもたないのか。
きみは咳ばらいをして、どこかのエライ先生みたいな口調で言う。
「死ねっていうのはだね、そんな事を言ってくる人間は地獄に落ちるということを意味するのだよ」
ぼくはちょっと笑えた。そうかもしれない。
「……でも、人にそんなことを言わせた方も、いけないのかな」
「そんなわけないでしょ」
きみは急に真剣に言った。
「きみがなにかしてもしてなくても、そんな事を言っていい理由にはならない」
いつもきみは、ぼくの代わりに怒ってくれる。ぼくのせいじゃないと言ってくれる。やっぱりほんとは、ぼくのせいなんだと思うけど。だから、きみは優しい。
「そうかな……」
でもだからといって、毎日は変わらない。また明日。戦場と戦場を行き来する毎日。そのあいだ、ひと時の優しい時間。
ぼくはだんだん、思うようになる。さわれないきみと融けあって、この踏切に立って。
死ね。
きみをすり抜け、ぼくをグチャグチャにする電車は、どこか幸せなところにぼくを連れて行ってくれるのではないかと。
*
なんで人は、こんなに残酷になれるんだろう。
放課後の教室、ぼくはいない。ぼくは遠くの踏切のことを考える。ふわふわ飛んでいく。するときみがいる。
「映画にはよく、悪役が出てくるよね、でも現実の悪者はそれよりもっと酷いことをする。なのに役じゃない」
きみはそんな事を言う。
「みんながきみみたいなユーレイなら良いのに」
「幽霊なんかいないけどね」
きみのそんな冗談がおかしくて、ぼくの頬がゆるむ。
「きみが天国にいけないなら、この世界はおかしいよ」
教室に斜めに差す光が眩しい。床は冷たいが手をすべらせると、その陽だまりが暖かい。
「大丈夫だよ」
きみはそんなふうに言って、ぼくを抱きしめる。電車がやってくる。きみは透明で、今はぼくも透明。音もなくやってきた電車が、ぼくらをすり抜けると、ぼくらのまわりを電車の車内が通り過ぎていく。赤い西日の差し込む車内の時間は止まっている。
気がつくと、ぼくは教室の床や、掃除ロッカーや、トイレや、体育館の倉庫に、くしゃくしゃの紙くずみたいに捨てられている。立ち上がる。暗くなる前に、はやく帰らなきゃ。
暗くなると、きみとはお別れ。だけど、気がつくと学校にいる間にもう日暮れになってしまう。
きみに会えない。きみがいない。
ぼくも、ユーレイになりたい。
*
その日、ぼくは家に帰るのがとても遅くなってしまった。ぼくの放課後はいじめられるのにいそがしい。帰るのが遅くなると夕食の準備も遅くなって、おかあさんを怒らせてしまうから、きっと怒っているんだろうなと思うと足が動かなくて、余計に遅くなった。
でもあんまり遅すぎたせいか、おかあさんはもう眠っていた。煙草とお酒の匂いが部屋に満ちていた。
薄暗く狭い居間に、おとうさんという人がいた。
おとうさんという生き物のことをぼくはよく知らなかった。そのあたらしいおとうさんとはあんまり話さないように避けていた。でもその日、おかあさんはすっかり眠っている。その人と目が合ってしまう。
なぜか優しそうに笑うのが、怖いと思った。
虐められてんのか。と煙草の火を消しながら言う。
ぼくがなにも言わずにいると、今度は来い、と言った。
戸惑いながらぼくは、一歩近づいた。二歩近づく。机の上にはビールの空き缶が何本も転がっている。
その人は急にぼくを引っ張る。
酒と煙草の混ざる腐ったような息の匂いが鼻をつく。
あれ、どうしてだろう。
なんで?
なんで、ぼくはきみにふれられないのに。きみはぼくにさわれないのに。こんな汚い手がぼくにふれるんだろう?
なんでだろう?
なんで人は、こんなに残酷になれて、なんでこんなに狂ってしまえるのだろう?
それとも、全部ぼくが悪いのだろうか。それなら、全部が納得できた。
「やめて、ください……」
つぶやく口が塞がれる。直ぐ側におかあさんがいる。襖の開け放された隣の寝室。ぼくは、自分にもどこにそんな力があるのか不思議なほどのちからを出してその手を逃れて、叫んだ。
「た、助けて、――おかあさん、助けて‼」
ぼくは、叫んでしまった。舌打ちと同時にぼくは殴られる。
お母さんは、うるさい! と呻いてから、ぼくたちの方を見る。
その一瞬の静けさに、ぼくはもうなにもできない、祈って、縋ることしか、手を伸ばすことしかできない。
ぼくはそれまで、心のどこかに、淡い期待があったんだ。ぼくは、忘れられなかった。ずっと昔、ぼくを抱きかかえて、桜の花みたいにぼくに笑いかけて、絵本を読んでくれたおかあさんのことを。このひとは、あのひとだということを、どうしても信じたかったんだ。
だけどおかあさんはものすごい勢いでぼくにあらゆるものを投げつけ、あらゆることばで罵倒した。ぼくを。ぼくはおかあさんから何もかもを奪うって。
お前は悪魔だ。死ね、地獄に落ちろ、お前みたいなバカ娘、産まなければよかった!
その時、涙がこぼれ落ちた。
おかあさんに言われた言葉が悲しくて、泣いたのは、それが二度目だった。一度目は、もっと前、そう、きみを初めて見た時。その日は、ぼくが怒らせてしまったおかあさんが、最初にぼくに死ねって言った日だった。
ぼくは弾かれたように家を飛び出した。涙があとからあとからこぼれて、ぼくは、声をあげて泣きながら走った。痛いほどの雨が降っている。
ここは、地獄だ。
裸足の足の裏が石を踏む。
きみとおんなじ、ぼくの青いセーラー服は、雨と誰かの狂気で、汚れて、擦り切れている。
きみが待ってる。
そうだよ。死んだら全部消える。
全ては生きている間にしか存在しないの。
だから大丈夫だよ。
きみが呼んでる。
雨の吹きつける踏切のランプが赤く点滅し、雨粒がそれを乱反射させる。けたたましく、警音が歪んで聞こえる。
そこに、きみが立っていた。
そこはいつも、ぼくに尋ねる場所だった。
歩き続けるか、立ち止まるか。
ふたつの道が重なりあう。生と死が、交差する場所。
「そっか、きみは……」
青いセーラー服。
まるで鏡合わせの、ぼくときみ。
目線の高さはいつの間にか揃っていた。ぼくはバーを潜り抜けて、踏切の中に入る。半透明なきみと向き合って、立ち止まる。
中学校に入って、少し調べればすぐ分かった。あの学校に、これまで、電車の事故で死んだ生徒は居ない。
なぜなら。きみは。
「……ユーレイじゃなかったんだ」
「ずいぶん、遅かったね」
きみはまた、ちょっと悪戯っぽく笑った。
ぼくはさいしょから、勘違いしていた。きみはぼくに、一度も嘘をついていなかった。ほんとうのことを、教えてはくれなかっただけで。
「うん。やっと、わかったよ」
それは今際の際に、極限に引き伸ばされる、半透明の幻。死へ、漸近していく無限の時間。
「……ぼくはね、きみに天国に行ってほしかった」
きみは言った。
「……どうして?」
ぼくは、天国にはいけない。ぼくはわるい子だから。地獄に堕ちるんだとおかあさんは、ぼくにいつもそう言った。きっとそのとおりだと思う。
ぼくはいつかねこを殺したし、さいしょのおとうさんがいなくなったのもきっとおかあさんの言う通りぼくのせいだし、みんなが死ねっていうぼくは、きっと悪い人なんだ。そしてまた、ぼくのせいで、きっと壊れた。ぜんぶ、ぼくが悪くって、ぼくはここにいちゃいけないんだ。
「ぼくは、きみだから」
でもきみはそう言った。涙がこぼれ落ちるのを頬に感じた。そうだ。
ぼくもきみに、天国に行ってほしいと思っていた。今も思っている。ぼくに唯一優しくしてくれた。それと同じなんだ。
檻のように閉ざされた踏切に、警音がこだまする。ぼやけていく、ゆがんでいく視界。雨と桜の花びらが降り注いでいる。
電車が近づく。ライトがぼくたちを明るく照らし出す。悲鳴みたいなブレーキの金切り声。
「だから、ぼくが地獄にいくよ」
きみは、ぼくの肩を押した。
ぼくの身体はよろめいて、線路の上から外れる。その一瞬、きみがぼくに笑いかける。最後に。
また、いつか。
ぼくがそうつぶやくと、きみはふっと視界を過る電車に融けて消える。
そしてぼくの両足は、猛スピードで廻る電車の車輪に骨ごと引きちぎられた。勢いでぼくのからだは吹っ飛んで、雨のしずくが、止まる。
極限の時間に、ぼくはきみを想い、ぼくはユーレイになる。
ずっと独りぼっちだったぼくに、ぼくは笑いかける。誰もくれなかった言葉をかける。誰かに言ってほしかった言葉を。怒れなかったぼくの代わりに、めいっぱい怒る。その笑顔のために、口下手なりにふざけてみる。きみは悪くないよ。きみが誰にもできなかった話を聞く。また明日。だれもくれなかった約束を、きみに捧げる。
誰も願わなかったことを、きみに。
全ては一瞬だった。
やっと、心からわかった。
きみはユーレイだったんじゃない。
きみはぼくだったんだ。
*
人は、死んだら消えてなくなる。全ては死ぬまでにしか起こり得ない。
世界はぼくに降り注ぐ冷たい雨で、きみはぼくの生と死の境目にゆらめいたユーレイだった。
きみは天国が嫌いで、ねこが嫌い。雨が嫌いで映画館が嫌いで、そしてなにより、きみは自分のことが嫌いだった。でもぼくは、そんなきみが好きだった。
この世界に神様はいなくて、もうきみもいない。天国も地獄もない。ぼくや、他の誰かが悪いことをしても、誰も裁いてはくれないし許してもくれない。
ぼくは今日もきみのために、透明な足で踏切を渡る。
いつもぼくはきみに訊いてばかりだったから、もしもまた会えたら、今度はぼくがきみに教えてあげたい。
足がなくても、ねこは寄ってくるってこと。ぼくは手を伸ばし、やわらかいねこの頭を撫でる。